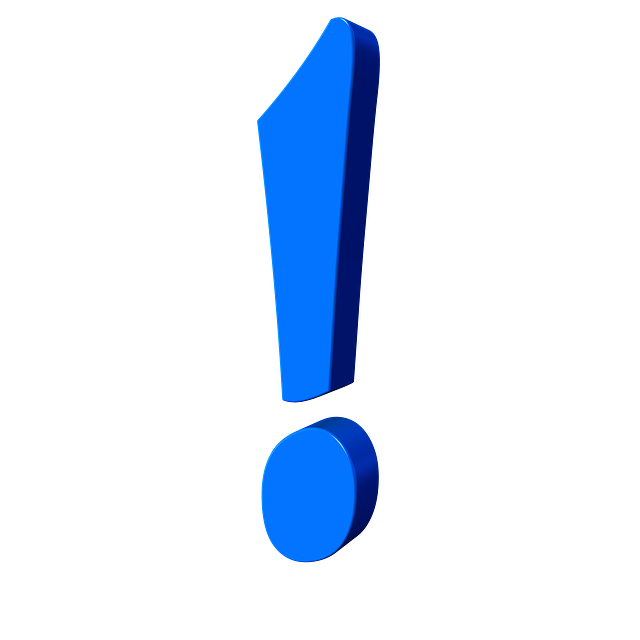【ニュースレター 2022 ❸ 民事訴訟法務】
民事訴訟法務
証 拠 保 全
入 門
- 証拠の改竄(かいざん)を阻止! -
今回のニュースレター2022第3回民事訴訟法務は、訴訟で絶対的に必要な証拠の確保という観点で、特に証拠の改竄阻止についての証拠保全事件を取上げます。
民事訴訟法第234条(証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
民事訴訟法は、裁判において、当事者が主張した事実を証拠に基づいて認定し、訴訟当事者の権利又は法律関係について判決をする手続きを規定しています。その判決をするための前提となるのか事実の存否です。そして、この事実の存否を判断するときに証拠が必要になります。
そのため、原告は、裁判で自身の主張を正当化するため、つまり、実体法上、自身には争われている権利又は法律関係が「ある」と裁判官に認めて貰う必要があります。
裁判官は
どのような思考回路で
目に見えない原告が主張する事実の存否を判断するのでしょうか
それは
当事者の合理的な意思解釈や経験則
そして
目に見える「証拠」で判断します
従って、原告としては、基本的に誰の目から見ても明らかな「証拠」の存在が必要不可欠になります。
しかし、現実問題として、いつも原告が証拠を確保しているわけではありません。また、被告としても、原告の主張する事実は存在しない事を反論や抗弁で主張しなければ、裁判官は原告の主張を認めてしまい、訴訟で敗訴する立場にあります。
場合によっては
被告が所持している
原告にとって有利な訴訟の証拠を改竄してしまう危険性さえあるのです
事実は一つですが
真実は人の数だけ有ります
裁判所は
客観的な真実を
つまり
一つの事実を誰の目から見ても一つの真実として明らかにし
正義を実現するところではありません
それは、裁判官にとって不可能を強いるからです。しかし、裁判官は、可能な限り、審理を尽くし、法廷で事実を明らかにしようとします。
そこで、民事訴訟法は、事実を明らかにする必要から、証拠保全手続きを規定しました。原告としては、主張する事実が証拠によって立証出来れば、原告の権利又は法律関係が存在する事が裁判官によって判断され原告勝訴の判決が得られます。
尚、裁判は、あくまでも事実を明らかにする手続きですが、それは本来、誰の目から見ても真実であるべきで、本来、訴訟当事者は正当な権利の実現を目的に裁判をするものです。原告側、被告側双方は、証拠を改竄したり、隠滅したりする事はもとより、その事を通じて、故意に正当な権利を否定させる行為をする事は、正当化できない事は言うまでも無い事です。
司法書士も弁護士も訴訟代理人として訴訟に携わる法律専門実務家は、原告や被告の真実の権利の実現を使命としており、依頼者の主張が真実ではない事が明らかになった場合は、訴訟代理人としての使命から、その後の訴訟方針を改めざるを得ない事は言うまでも無い事です。何故なら、法は悪に手を貸さないからです。
このニュースレターでは、証拠保全とはとのような事か、証拠とは何を指すのか、証拠調べとはとのような意味か、という原告が訴訟を提起する前提と、その証拠保全方法について要説を概説します。
ご覧の皆さんは、自身の権利が正当に認められ、その権利が行使出来る為には、法律上、どのような手立てがあるのかについて参考にして下さい。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
<CONTENTS>
■証拠保全事件とは
■文書改竄阻止の為の証拠保全事件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■証拠保全事件とは
●証拠調べと証拠方法
証拠調べとは、裁判所が証拠を取り調べる事をいいます。
それでは、証拠とはなんでしょうか。
民事訴訟は、当事者間の紛争につき、裁判所が、事実を認定し、それに法律を適用して、結論を導き出す手続です。ある事実の存否について裁判所が十分な心証を得られた状態、あるいは、裁判所にそのような心証を得させるために当事者が訴訟において資料を提出する行為のことを立証又は立証活動といい、立証に用いられる資料のことを証拠といいます。
そして、民事訴訟では、この立証に用いられる資料(証拠)は、証拠調べの際、色々な方法によって提出される事から、この証拠調べの際の資料、つまり、証拠調べの対象となる証拠の事を「証拠方法」といっています。
証拠調べの対象となる証拠 = 証拠方法
証拠方法とは
証拠調べの際の証拠の提出の仕方
つまり
証拠対象の種類形式の事
●証拠方法
訴訟で立証に用いられる資料を証拠といい、証拠調べの対象を証拠方法といいますが、証拠方法には、大きく分けて人的証拠(人証)と物的証拠(物証)に大別されます。
人的(じんてき)証拠(人証=じんしょう又はにんしょう)には、証人、当事者及び鑑定人があり、物的(ぶってき)証拠(物証=ぶっしょう)には、文書及び検証物があります。
証拠方法には
人証と物証が有る
▼人的証拠(人証)
証人を証拠方法とする証拠調べを証人尋問、当事者を証拠方法とする証拠調べを当事者尋問、鑑定人を証拠方法とする証拠調べを鑑定といいます。証人は体験した事実を証言する者であり、鑑定人は専門知識やそれに基づく意見を証言する者ですので、証人には代替性はなく、鑑定人には代替性があるという事になっています。
尚、鑑定人とは、鑑定の対象となる証拠に対する専門的知見を証言する者をいい、鑑定される対象者の事ではありません。
▼物的証拠(物証)
文書を証拠方法とする証拠調べを書証といい、検証物を証拠方法とする証拠調べを検証といいます。
文書と検証物の違いですが、例えば、同じ文書の証拠調べでも、その意味内容を証拠調べの対象とするときは書証であり、その外形や形状を証拠調べの対象とするときは検証となります。
●証拠資料
証拠調べの結果、得られた資料の事を証拠資料といいます。
証拠調べの結果得られた資料を
証拠資料という
人的証拠では、証人尋問の証拠資料は証人の証言、当事者尋問の証拠資料は当事者の供述、鑑定の証拠資料は鑑定人の鑑定意見となります。
物的証拠では、書証の証拠資料は文書の内容、検証の証拠資料は検証の結果となります。
●証拠原因
裁判官の心証形成の原因となった資料を証拠原因といいます。
証拠原因には、全ての証拠調べ、つまり証人尋問、当事者尋問、鑑定、書証、検証の結果と弁論の全趣旨があります。
●証拠能力と証拠価値
訴訟に提出されたある資料を事実認定のために利用し得る適格性の事を証拠能力といいます。換言すれば証拠となる資格の事です。民事訴訟においては、証拠能力はきわめて広範に認められ、基本的に証拠能力に制限はありません。但し、著しく反社会的な手段を用いて収集された資料等は証拠能力が無い場合があります。
ある証拠がそれによって証明したい事実の認定にどの程度役立つかという評価のことを証拠価値といいます。証拠によってその証拠価値は様々であり、証拠価値をどう評価するかについては、裁判官の自由な判断に委ねられています(自由心証義)。
●証拠保全において可能な証拠調べ
証拠保全手続きについては、特別な規定は存在せず、証拠保全における証拠調べの方法に条文上の制限はありません。人的証拠でも物的証拠でもあらゆる証拠方法につき認められるので、証拠保全で調査嘱託を申立てる事も理論上は可能です。調査嘱託とは、公正さを有すると考える団体に対し、手元にある資料に基づき容易に調査する事が出来る客観的事項について調査を嘱託して、その調査の結果を証拠資料とする、簡易・迅速な証拠調べをいいます。
尚、調査嘱託は、提訴前証拠収集処分として申立てる事もできますが、提訴前証拠収集処分を申立てるには、予め適式の提訴予告通知をしなけらばならないので、緊急性があるような場合には、証拠保全を選択する方が良いと思われます。
証拠収集処分は、当事者の証拠収集を裁判所が一定範囲で補助する制度であり、証拠の所持者がその証拠の提出に非協力的であるような場合に、一定の有用性がある制度です。証拠保全と証拠収集処分は、証拠に対する制度という意味では同じですが、各々利用範囲やその有効性は、その事件での必要性及び重要性との関係で使い分ける事が必要です。
医療事件や労働事件のように、訴訟の相手方に証拠の大部分が偏在している事件では、証拠の保全が必要であり重要なので、証拠保全手続きが多く利用されています。
●証拠保全の要件
それでは、証拠保全をするためには、法律上、どのような事由が必要なのでしょうか。
それは、「予め証拠調べをしておかなければその証拠を使用する事が困難となる事情」の存在です。これが証拠保全の要件であり、具体的な事情を証拠保全の事由といいます。
具体的な証拠保全の事由としては、人的証拠については、証人の余命、海外渡航の急迫、外国人の帰国等が挙げられ、物的証拠については、文書、検証物の滅失、散逸、保存期間満了等による廃棄、改竄、性状又は現状変更の恐れ等が挙げられます。
また、証拠保全の事由には、証拠保全の対象物(証拠方法)が存在する事も含まれると解されています。証拠が不存在であれば、証拠保全を観念出来ない為です。
●証拠保全申立事件
最も多い証拠保全申立事件は、検証になります。1994年(平成6年)から2003年(平成15年)までの東京地方裁判所に申立てられ、実際に証拠保全の決定をした証拠保全の90%以上が検証との事です。また、東京地方裁判所の申立てられた証拠保全における検証の割合は、2006年(平成18年)から2008年(平成20年)までに約90%、2009年(平成21年)から2012年(平成24年)までで約85%となっているとの事です。
そして、検証の目的ですが、医療機関を相手方をして診療録(カルテ)等の検証を求める証拠保全の割合が最も多く、次いで労働事件等となっています。但し、医療事件における証拠保全の申立て件数は、減少傾向にあり、その理由として主たる医療機関を中心に診療録の任意開示制度の充実が挙げられています。
■文書改竄阻止のための証拠保全事件
●証拠保全における書証の方法による選択基準
基本的には、証拠保全の事由を「廃棄・散逸のおそれ」とする場合は、書証の方法による事が、「改竄のおそれ」とする場合は、検証の方法による事が考えられます。
つまり、申立人としては、想定される証拠保全の事由との関係で、対象となる文書について、文書の意味・内容だけを保全するれば足りすのか、それとも文書に施された修正の有無等の形状についても保全する必要があるかを前提に、証拠調べの方法を選択する事になります。
尚、証拠の必要性及び重要性の有無の判断は、本案訴訟の審理を行う裁判所が行う為、証拠保全の裁判所は、原則としてこれを判断すべきでなないとされています。
●証拠保全申立ての種類
証拠保全手続きは、訴えの提起前における証拠保全手続きと訴えの提起後における証拠保全手続きの2種類があります。
証拠保全手続きは2種類
訴えの提起前における証拠保全手続き
と
訴え提起後における証拠保全手続き
民事訴訟法第234条(証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用する事が困難となる事情があると認めるときは、当事者の申立てにより証拠調べを行います。
つまり、証拠保全手続きは、訴訟提起前でも訴訟提起後でもする事が出来ます。
「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用する事が困難となる事情」が要件ですが、例えば、訴訟提起後では、相手方も訴訟戦略や訴訟戦術を前提とし、攻撃防御方法の検討に入った言わば臨戦態勢を執りますので、訴訟係属中に判明した証拠を対象にする場合は除き、通常は訴え提起前の証拠保全申立てが多く、訴訟が進行するに従って、明らかにしなければならない事実や隠滅や改竄の恐れの無い証拠は、訴え提起後でも証拠保全の申立てが出来るという理解が一般的ではないでしょうか。
●管轄裁判所(民事訴訟法第235条)
▼訴え提起前の証拠保全手続き
訴えて提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければなりません。
▼訴え提起後の証拠保全手続き
訴えて提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければなりません。但し、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続き若しくは書面による準備手続きに付された後、口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければなりません。
尚、急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、訴え提起前の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをする事ができます。
●証拠保全の申立て方式(民事訴訟規則第153条)
▼証拠保全の申立て事項
証拠保全の申立ては、書面でしなければなりません。この書面には、次の事項を記載しなければなりません。証拠保全の事由は疎明しなければなりません。
〇相手方の表示
〇証明すべき事実
〇証拠
〇証拠保全の事由
▼証拠保全申立書の標題形式
〇申立ての趣旨
〇申立ての理由
▽証明すべき事実
▽証拠保全の事由(事情、保全の必要性、結論)
〇疎明方法
▽疎明資料(陳述書、証明書等各2通)
▽付属書類(疎明資料写し、訴訟委任状等各2通)
▼目録
〇当事者目録
〇検証物目録
●検証とは
検証とは、裁判官が五官の作用によって事物の形状・性質・現象・状況を感得し、その判断内容を証資料とする証拠調べの一方法です。
つまり、物的証拠では、文書と検証物がありますが、その証拠調べの方法として、書証は文書の内容であり、検証は検証物である文書の客観的変化の有無、言換えると文書の信頼性を保持する事を目的として取調べをする事になります。
検証の目的は
文書の信頼性の保持
文書の改竄阻止のための証拠保全手続きにおける証拠方法は、検証になります。
●検証の証拠保全申立て手続き
▼事案の相談
↓
▼証拠保全の必要性・重要性判断
↓
▼「証拠保全申立書」起案
↓
▼管轄裁判所に証拠保全の申立て
↓
▼担当裁判官による証拠保全申立書の形式的、実質的審査
※証拠保全申立書について、証拠保全の事由で、証拠保全の必要性の疎明内容が不十分であったり、陳述書の射程が外れているような場合には、申立書の記載の補充や陳述書の追完が指示されます。この場合は、管轄裁判所に申立補充書及び陳述書追完を提出します。
↓
▼担当裁判官面接期日
※面接では、一般的に、証拠保全申立書の補足説明及び疎明資料の原本確認の他、証拠調べの具体的な実施方法及び実施期日並びに決定書及び呼出状の相手方に対する送達方法等の事務的な打合せをする事になります。
↓
▼証拠保全決定発令
↓
▼証拠保全決定書謄本受取り
↓
▼証拠調べ期日の期日請書を担当書記官に提出
↓
▼担当書記官から担当執行官へ執行官送達依頼書及びその他の関係書類を交付
※その他の書類
〇証拠保全決定書謄本
〇証拠保全申立書副本
〇疎明資料
〇証拠調べ期日の呼出状
〇証拠保全手続きについての説明書
↓
▼執行官室の担当執行官に執行費用を予納
↓
▼証拠保全の証拠調べ期日当日
※関係者全員が検証場所に集合します。
※手続き自体は、裁判所が主宰します。
↓
▼検証場所で執行官が相手方へ証拠保全決定書等を渡す
↓
▼執行官が送達報告書を申立人に手渡しし、裁判所に送達が完了した旨を架電
↓
▼送達完了の入電後、担当裁判官及び担当書記官が管轄裁判所から検証場所へ到着
↓
▼担当裁判官等は執行官から送達報告書を受取り
↓
▼担当裁判官及び担当書記官が検証場所へ臨場
↓
▼相手方から関係書類を提出して貰い、検証開始
※相手方から関係書類(検証物)を提出して貰い、担当裁判官が書類等の形状、体裁、記載内容等を確認した上で、その後、書類等の写真撮影やコピーを行い、撮影した写真等の資料を裁判所で保管する手続きになります。
尚、相手方が関係書類の提出を拒否した場合に備え、検証物提示命令の準備をしておきます。
↓
▼証拠保全事件の終了(検証手続終了)
↓
▼担当書記官による検証調書作成
※1カ月程度で検証調書が作成されます。検証調書は、担当裁判官認印押印で作成が完了します。
↓
↓※本案訴訟提起
↓
▼原告が口頭弁論期日にて証拠保全手続きの証拠調べの結果を上程
※証拠保全手続きの検証方法による証拠調べの結果を口頭弁論に上程すれば、これにより本案訴訟において証拠調べがされたのと同一の効力生じる事になります。
いかがでしたでしょうか。
証拠保全手続きは、医療事件や労働事件といった相手方に証拠の大部分が偏在しているような事件に有用性があります。是非、この機会にイメージが掴めるようにして頂ければと思います。
特に労働事件では、就業規則、労働契約書、タイムカード、業務日誌、業務メモ、コンピューターの印字データ、ログ等自身で確保出来る証拠も多く有ります。証拠保全の申立ても、その証拠保全の要件が具備されていなければ認められません。その意味で、証拠は出来るだけ自身で確保しておく事をお勧めします。
そして、ご相談は、民事訴訟法務を専門分野又は取扱分野としている法務事務所の司法書士にご相談下さい。
最後は法律的解決しかありません あなたには最後の手段が残っています
※「民事訴訟法務」とは
「民事訴訟法務」とは、訴訟費用が比較的低額で、自身の権利の主張が有用な「本人訴訟支援」を原則に、簡易裁判所における訴訟代理権に基づく「訴訟代理法務」により、依頼者の権利の実現を目的とした法律支援実務です。
司法書士の「本人訴訟支援法務」は、「訴訟代理法務」とは異なり、裁判所等に提出する書類作成関係に関しては、取扱う事件に制限は有りません。
また、簡易裁判所管轄で、訴額が140万円以内であれば、訴訟代理人としての受任も可能です。
※「本人訴訟支援法務」と「訴訟代理法務」とは
「本人訴訟支援」とは、一般的な法律相談の他、法律専門実務家である司法書士が、依頼者の意思決定に基づき、依頼者に代わり、依頼者から事情聴取をしならが裁判所等に提出する訴状や答弁書等の書類作成を中心に、いかに依頼者の権利が正当に判断されなければならないかを権利擁護者として、裁判手続等を通して支援する法律上の業務です。そして、司法書士の「本人訴訟支援」は、裁判所等に提出する書類作成に関しては、取扱う事件に制限は有りません。
「訴訟代理法務」とは、一般的な法律相談の他、簡易裁判所管轄で、訴額140万円以内の事件において、司法書士が依頼者の訴訟代理人として、依頼者と協議をしながら、司法書士自身が主体的に裁判手続きをする民事上における法律上の業務です。
一般的に、「訴訟代理法務」に比べて「本人訴訟支援法務」の方が、裁判手続に掛かる費用が低額で済み、法律問題の解決を図る事が出来ます。「本人訴訟支援法務」の事件対象は、比較的複雑でない生活関係、家族関係(身分関係)、仕事関係、事故関係、迷惑行為等の不法行為関係といった日常的に生じる法律事件に有効です。
※「認定司法書士」とは
「認定司法書士」とは、訴訟代理資格を修得するための特別の研修を修了し、その認定試験に合格した簡裁訴訟代理等関係業務法務大臣認定司法書士の事を言います。民事における法律事件に関する訴訟代理の専門性は公式に認められています。
※「簡裁訴訟代理等関係業務」とは
「簡裁訴訟代理等関係業務」とは、簡易裁判所において取扱う事が出来る民事事件(訴訟の目的の価格が140万円以内の事件)についての訴訟代理業務等であり、主な業務は次の通りです。
①民事訴訟手続き
②民事訴訟法上の和解の手続き
③民事訴訟法上の支払い督促手続き
④民事訴訟法上の訴え提起前における証拠保全手続き
⑤民事保全法上の手続き
⑥民事調停法上の手続き
⑦民事執行上の少額訴訟債権執行手続き
⑧民事に関する紛争の相談、仲裁手続き、裁判外の和解手続き
(2022年8月1日(月) リリース)